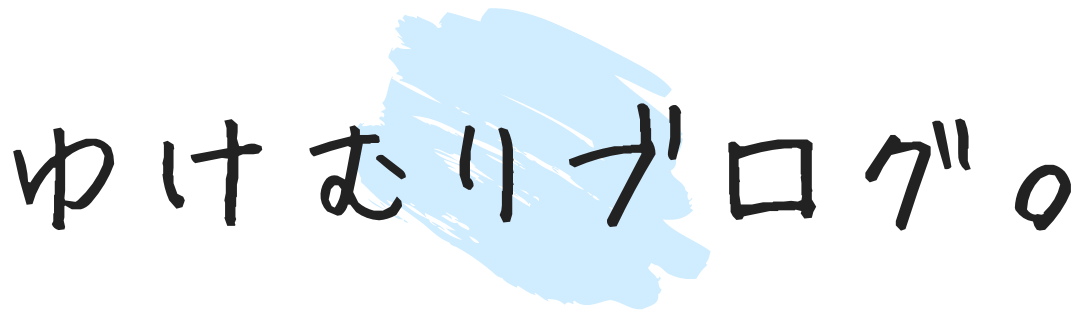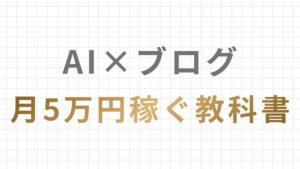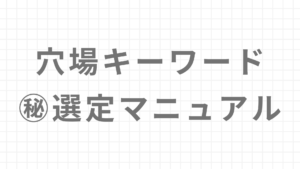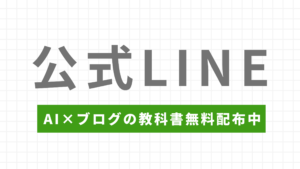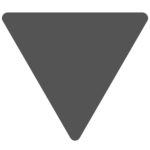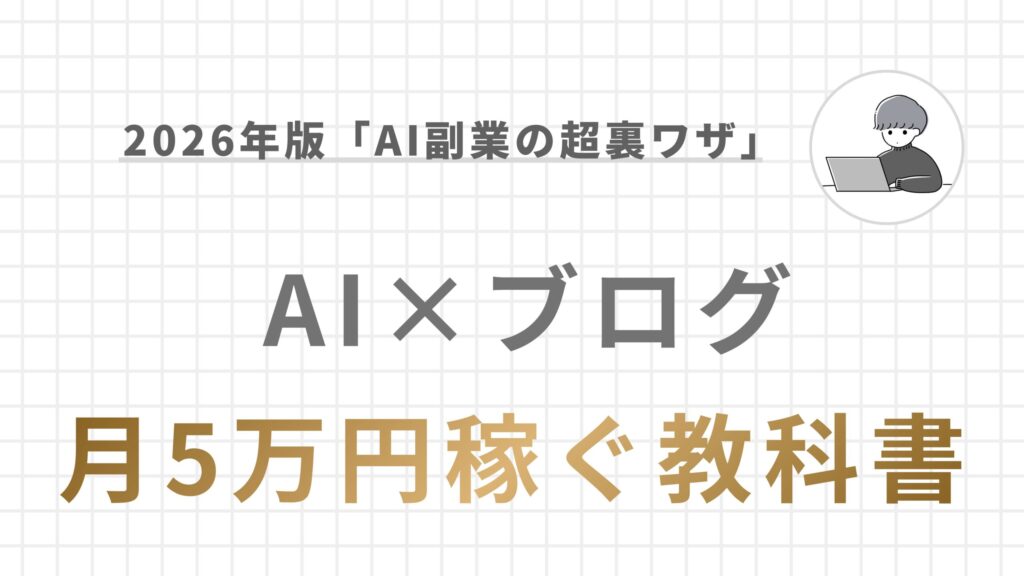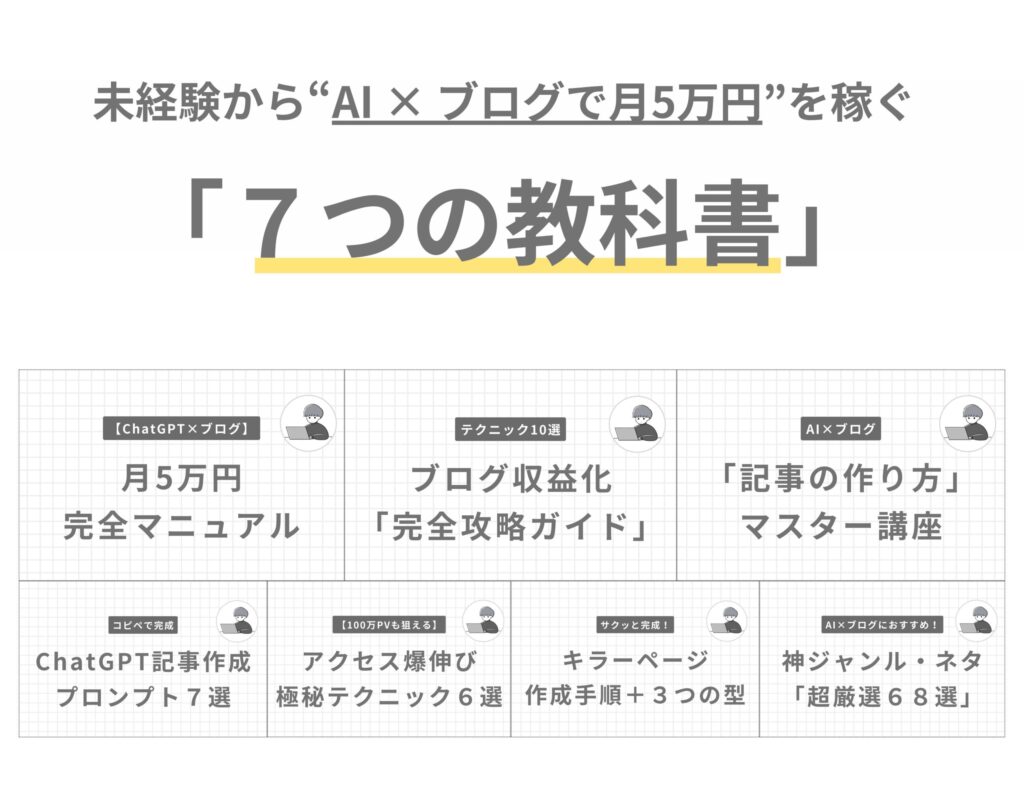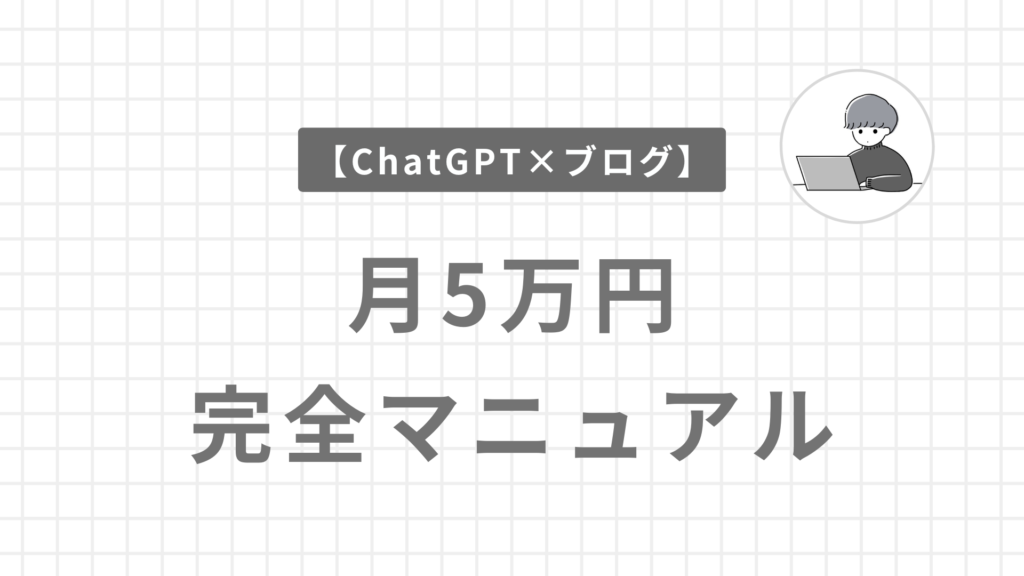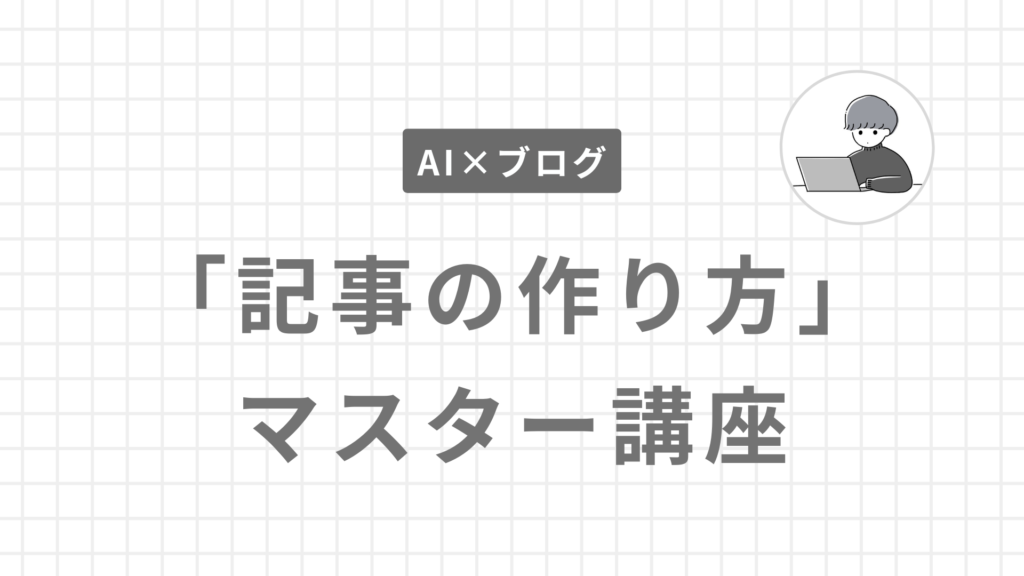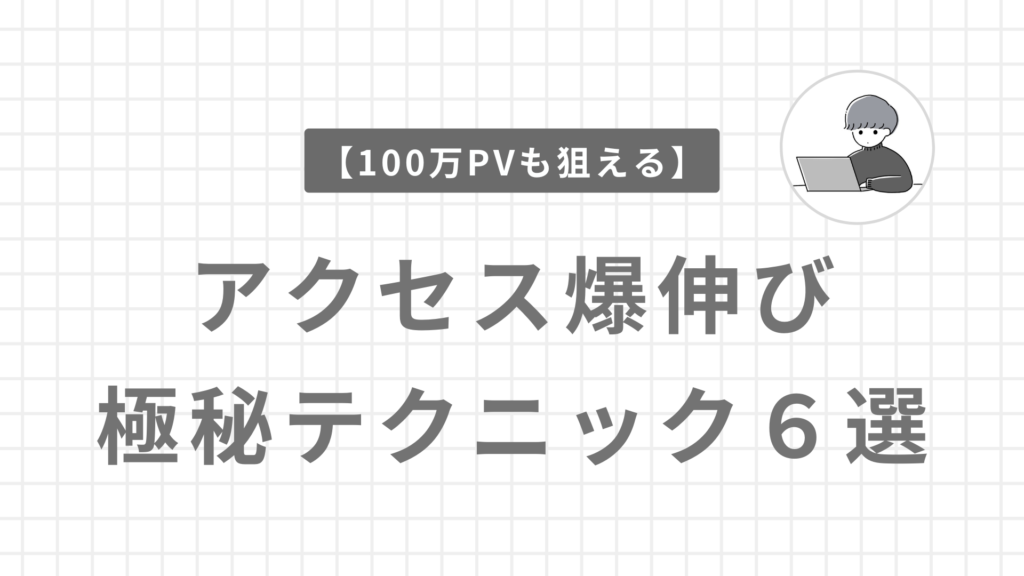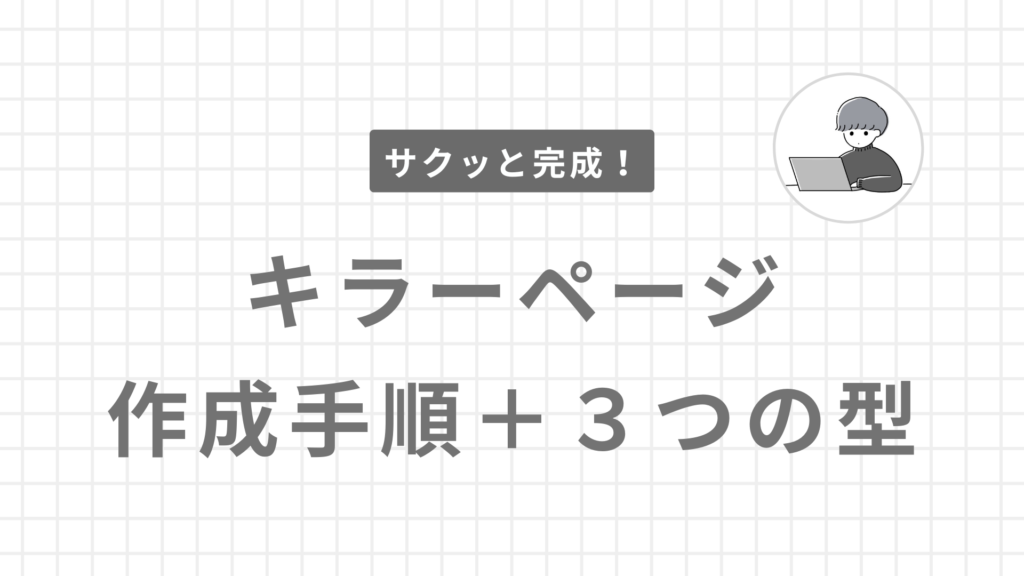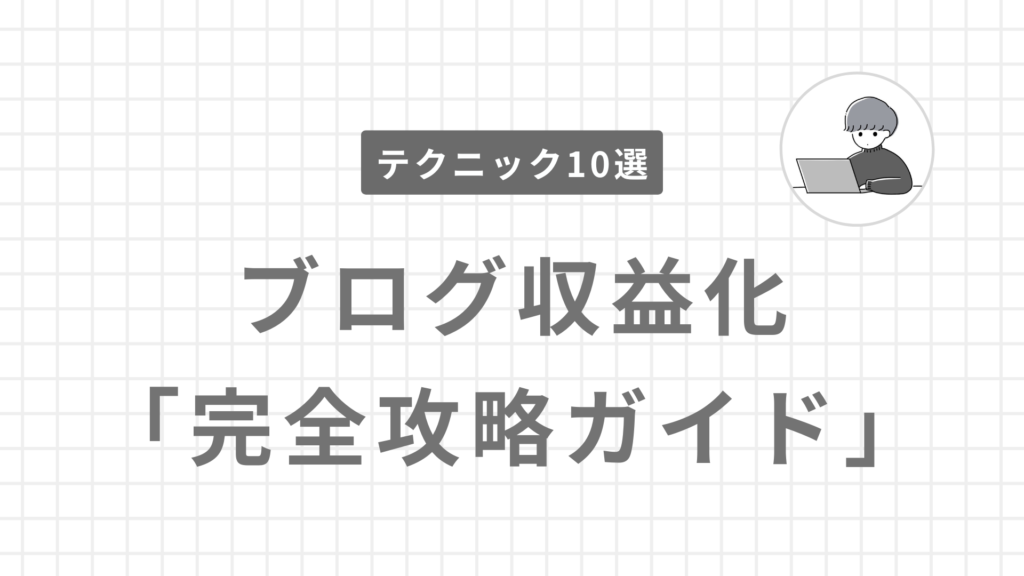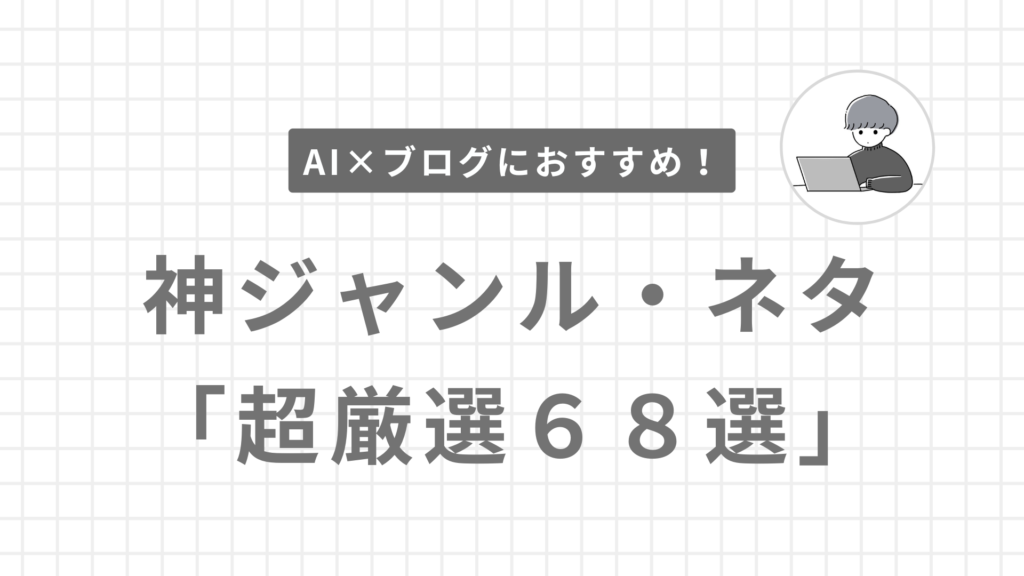- note以外に使いやすいブログサービスを探している
- noteだと収益化しづらいと感じている
- 自分に合った発信スタイルを見つけたい
こんな悩みを全て解決していきます。
noteは便利なプラットフォームですが、目的によっては他のサービスの方が合っていることもあります。
この記事では、代わりになるブログサービスを7つの視点で比較しています。
「もっと自由に書きたい」「収益化も考えている」そんな方はぜひ参考にしてみてください。
目次
- 1 note類似サービス徹底比較!7の特徴
- 2 Q&A「note 類似サービス」に関するよくある疑問・質問まとめ
- 2.1 Q1. noteみたいなサービスって他にもある?
- 2.2 Q2. noteの代わりになるブログサービスはどれがいい?
- 2.3 Q3. noteに似た海外のサービスってある?
- 2.4 Q4. 無料で使えるnoteっぽいブログはある?
- 2.5 Q5. noteとBloggerってどう違うの?
- 2.6 Q6. 初心者におすすめのnoteみたいなサービスは?
- 2.7 Q7. note以外で人気のブログサービスってある?
- 2.8 Q8. note以外のブログサービスを一覧で比べたいんだけど…
- 2.9 Q9. noteをやめて他のブログに移るメリットってある?
- 2.10 Q10. noteみたいなサービスで収益を出すにはどうすればいい?
- 3 まとめ
- 4 「AI×ブログの教科書」を公式LINEで無料配布中
note類似サービス徹底比較!7の特徴
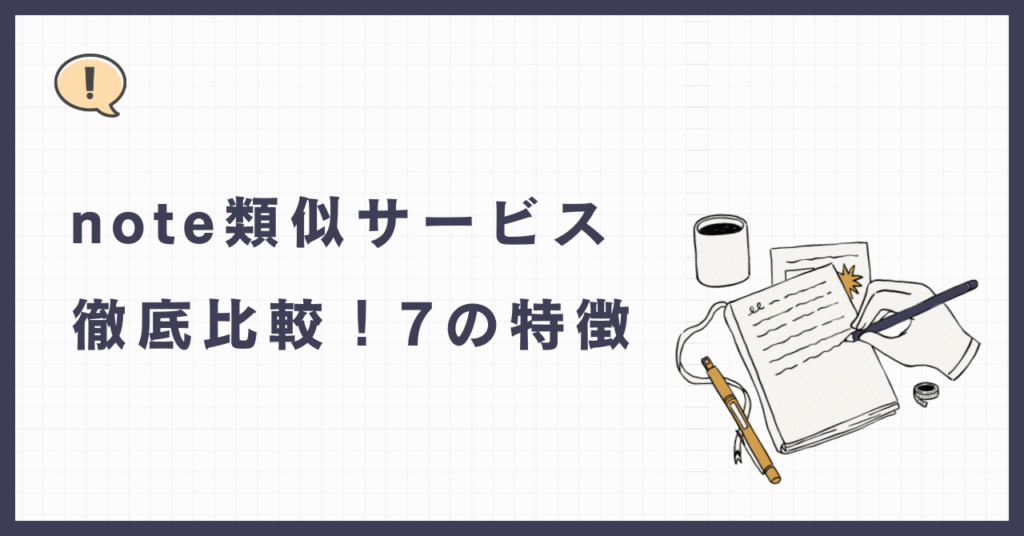
「note類似サービス」特徴:1. 誰でもすぐに書いて公開できる
登録してすぐに記事を書き始められる手軽さは、noteと同じく他の無料ブログにもあります。
難しい設定がなく、思いついたことをすぐに発信したい人に向いています。
たとえば・・
- はてなブログ:登録後すぐに記事投稿可能
- Amebaブログ:スマホからでも手軽に更新できる
- ライブドアブログ:シンプルで広告も入れやすい
💡「書くこと」に集中できるシンプルな構成が魅力です。
文章力を磨いたり、習慣化するには最適な入り口になります。
自由度は低めなので、デザインを変えたり、細かい機能を追加したい人には物足りなさを感じるかもしれません。
「note類似サービス」特徴:2. 自由にデザインできる
見た目や構成にこだわりたい場合は、WordPressのような自由度の高いブログが適しています。
noteではできないレイアウト変更や導線設計が可能です。
具体的には
- レイアウト、色、フォントまで自由に設定可能
- オリジナルの導線設計ができる(CTA、LPなど)
- 自分のブランドサイトとして育てられる
💡 読者に伝えたい情報を、自分なりの構成で配置できるのが大きなメリットです。
ブランドイメージを表現したい方にもぴったりです。
設定や操作には少し学習が必要なので、完全初心者は最初に軽く学ぶ時間を取るとスムーズに使いこなせます。
「note類似サービス」特徴:3. 無料で始められる
初期費用をかけずにブログを始めたい人には、無料プランのあるブログサービスが適しています。
書くことを体験しながら、自分に合っているか確かめるのに向いています。
たとえば・・
- FC2ブログ:広告が入るが完全無料
- はてなブログ(無料プラン):機能は限定されるが十分使える
- Amebaブログ:スマホ中心でも手軽に発信できる
💡 手軽にスタートできるので、継続できるか不安な初心者でも安心です。
必要なら後から有料プランに移行することもできます。
無料プランは機能に制限がある場合が多く、広告が表示されたり、収益化に不利なケースもあるため注意が必要です。
「note類似サービス」特徴:4. 広告やアフィリエイトで稼げる
コンテンツ販売に限らず、広告やアフィリエイトで収益を得たい人には、より多機能なブログサービスがおすすめです。
収益化の幅が広がることで、安定収入も目指しやすくなります。
たとえば・・
- WordPress:Google AdSenseやASP広告を自由に設置可能
- はてなブログ(Pro):アフィリエイトがしやすい設計
- FC2ブログ:広告OK、自由に貼れるスペースあり
💡 自分の商品がなくても、他人の商品を紹介して報酬を得られる点が魅力です。
アクセス数に応じた収入アップも期待できます。
ある程度のアクセスを集めないと収益にはつながりにくいため、SEOや読者ニーズを意識した記事作成が重要になります。
▼「アフィリエイトブログ」について、知りたいという方は以下の記事をご覧ください。
アフィリエイトブログの始め方|副業で月5万円稼ぐ完全マップ
「note類似サービス」特徴:5. 長く使えるブログ資産になる
プラットフォームに依存せず、自分のブログを持つことで記事が「資産」として蓄積されていきます。
1年前に書いた記事でも、読まれて収益になる可能性が十分にあります。
具体的には
- WordPress:記事がGoogle検索に強く、蓄積された価値が残る
- 独自ドメイン:ブログが「自分のメディア」として育つ
- 自由なバックアップ・移行が可能
💡 ブログに書いた情報がGoogleなどの検索に引っかかれば、半自動で読者が集まるようになります。
コツコツ積み上げれば、放置していてもアクセスが入る状態も夢ではありません。
初期構築や記事の設計にはある程度の戦略が必要です。
始める前に「誰に向けて、どんな情報を発信するか」を明確にしておきましょう。
「note類似サービス」特徴:6. 初心者でも始めやすい
ブログ初心者でも迷わず始められるシンプルなサービスが多くあります。
noteと同じように、文章を書くことに集中できる設計になっているものが多いです。
たとえば・・
- Amebaブログ:直感的なUIでスマホ更新もラク
- はてなブログ:シンプルな画面で書きやすい
- note:SNS感覚で投稿できる
💡 操作に迷わず、短時間で1記事目が書ける環境は、継続のモチベーションにつながります。
スマホだけでも投稿できるのも魅力です。
簡単さの反面、自由度や機能性が物足りなく感じることもあります。
ステップアップしたい場合は、早めに移行を検討するとよいでしょう。
「note類似サービス」特徴:7. 文章以外の発信もできる
ブログ以外にも、画像・音声・動画などのコンテンツを取り入れることで、より多くの読者にリーチできます。
noteではできない発信方法も他サービスなら可能です。
具体的には
- ブログ+YouTubeやstand.fmなどを連携
- WordPressでは埋め込みも自由自在
- SNSとの組み合わせで拡散力アップ
💡 発信スタイルを増やすことで、自分に合った表現方法が見つかりやすくなります。
ブログ+SNS、ブログ+音声などの組み合わせも有効です。
複数の媒体を使い分けるには、運用の手間や管理も必要になります。
無理なく続けられるスタイルを見つけることが大切です。
Q&A「note 類似サービス」に関するよくある疑問・質問まとめ
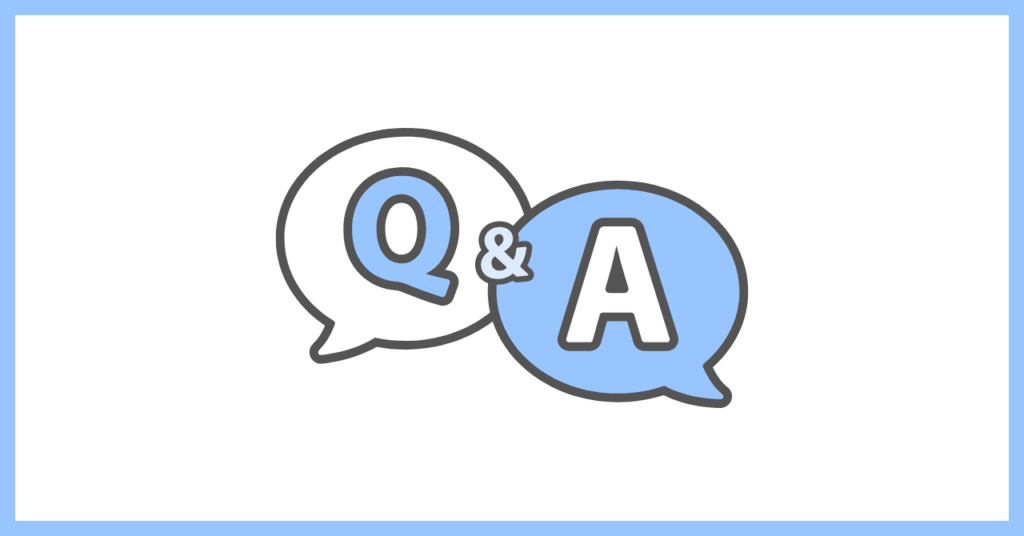
Q1. noteみたいなサービスって他にもある?
はい、あります。
たとえば「はてなブログ」や「ZINE」、「WordPress」なども、noteのように記事を書いて発信できます。
目的に合わせて使い分けると便利です。
Q2. noteの代わりになるブログサービスはどれがいい?
「もっと自由に作りたい」ならWordPress、「すぐ書きたい」ならはてなブログやAmebaブログがおすすめです。
自分のスタイルに合うものを選ぶのが大事です。
Q3. noteに似た海外のサービスってある?
はい、海外だと「Substack」や「Medium」がnoteに近い使い方ができます。
特に英語で発信したい方には人気です。
Q4. 無料で使えるnoteっぽいブログはある?
あります。
はてなブログ、Amebaブログ、FC2ブログなどは、登録するだけですぐに始められて、料金もかかりません。
Q5. noteとBloggerってどう違うの?
noteは有料記事の販売に向いていて、BloggerはGoogleの広告(アドセンス)を貼って収益化しやすいのが特徴です。
収益の仕組みが少し違います。
Googleアドセンスとは、Googleが提供する広告配信サービスです。
運営しているブログにタグを貼り付けると、読者にマッチした広告が配信されます。
出典:【完全初心者向け】Googleアドセンスとは?仕組みや稼ぎ方、登録方法を解説! – 初心者のためのブログ始め方講座
Q6. 初心者におすすめのnoteみたいなサービスは?
「とにかく簡単に始めたい」ならAmebaブログやはてなブログがいいですよ。
スマホからでも更新しやすいので、続けやすいです。
Q7. note以外で人気のブログサービスってある?
WordPressは特に人気があります。
自分のサイトを自由に作れるので、長く続けたい人に向いています。
Q8. note以外のブログサービスを一覧で比べたいんだけど…
この記事のように「特徴別」で比較されていると、自分に合うブログが見つけやすいです。
一覧で見ると違いがよくわかります。
Q9. noteをやめて他のブログに移るメリットってある?
あります。
たとえば、自分だけのブログを作れたり、広告を貼れたり、収益の方法が広がります。
長く続けたい人にはメリットが多いです。
Q10. noteみたいなサービスで収益を出すにはどうすればいい?
まずは「誰に何を伝えるか」をはっきりさせて、定期的に発信を続けることが大事です。
サービスによって稼ぎ方が違うので、自分に合った方法を選ぶといいですよ。
まとめ
noteは気軽に始められて便利ですが、「もっと自由に書きたい」「収益化もしたい」と感じているなら、他のブログサービスを検討するのもおすすめです。
特にWordPressのような独自ブログは、自由度が高く、しっかり育てれば大きな収益にもつながります。
また、初心者の方は、まずは無料ブログから始めてみるといいでしょう。
自分に合った発信スタイルを見つけながら、少しずつステップアップしていくのがコツです。
そして今、ブログを続けるうえで注目されているのが「AIを使ったブログ運営」。
うまく活用すれば、作業の負担を減らしながら、効率よく成果を出すこともできます。
「もっと具体的な進め方を知りたい」と感じた方は、以下のAI×ブログの教科書7本セットをチェックしてみてください。
AI×ブログの教科書一覧(全7本 無料配布中)
- 【ChatGPT×ブログ】月5万円完全マニュアル
- ChatGPT記事作成プロンプト7選
- AI×ブログ「記事作成マスター講座」
- 100万PVも狙える!アクセス爆増テクニック6選
- キラーページの作り方「完全ガイド」+3つの型
- ブログ収益化「完全攻略ガイド」+テクニック10選
- 2025年最新!AI×ブログおすすめ神ジャンル・ネタ68選
→ 7本の記事を全て無料で受け取る(期間限定)